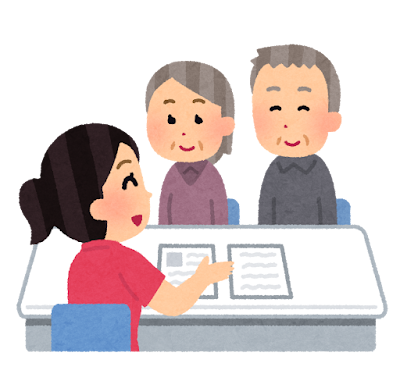COLUMN
2025.04.08企業再生・経営
円滑な事業承継のために「遺言信託」の活用を ~自社株の準共有~
- 事業承継
執筆者:株式会社日税経営情報センター
1.株式は法定相続分通りに当然帰属するのか?
相続人が複数名存在する場合、相続対象となった株式は誰にどのように帰属するのでしょうか?
【事例】
相続対象となった株式が100株
相続人が配偶者と子供2名
の場合
遺産分割を経ずともと法定相続分に従い配偶者に50株(1/2)、子供は各25株ずつ(1/4)に当然に分割されると考えるかもしれません。
しかし、これは間違いです。現行法の解釈としては、遺産分割協議によって株式の帰属を決めない限り分割されることはありません。
遺産分割協議がまとまらない段階で、株式に関する権利関係は法定相続分通りで準共有することになり、上記例でいえば、配偶者が1/2、子供は各1/4の割合で共有します。
あくまでも「準共有」であって、相続人に単独帰属するわけではありません。
1人の子供が1/4の割合を共有しているから、1/4相当分の議決権を行使する、あるいは配当の1/4を先に支払え等の具体的要求を行えるわけではないことに注意が必要です。
2.遺産分割前に株主権を行使するには?
上記で記載した通り、遺産分割前の段階では、各相続人が単独で株主権を行使することは不可能です。
株主権を行使したい場合、相続人間で協議を行い、権利行使者1名を選任の上、会社に通知した上で権利行使を行う必要があります(会社法第106条)。
この協議の方法ですが、法定相続分の多数決によって決めることが可能と解釈されています。
したがって、上記例でいえば、基本的には1/2の割合を有する配偶者の意向により多数決の結果が生じることになりますが、子供2名が協力しあった場合、配偶者1/2・子供たち1/2となり多数決とはなりません。
人数割りで多数決が決まるわけではないことに注意が必要です。
3.あらかじめ株式を相続する者を指定しておくべきこと
以上のとおり、共同相続人間で権利行使者を指定して会社に通知することで、遺産分割協議が整うまでの間、相続した株式について権利行使することができます。
しかし、親族間で仲が悪く、誰を指定するかについて共同相続人間で協議がまとまらず、どの共同相続人も過半数をとることができない場合は、権利行使者の指定・通知はできません。
これは、被相続人が大株主である会社の場合、特に問題です。
たとえば、判例上、相続された株式も定足数の母数に入れるとされているため(上記の最高裁判決 平成27・2・19)、権利行使者の指定・通知ができないと、株主総会の定足数を充たさず、株主総会を開催できないことになり、会社の意思決定が滞ってしまうというおそれがあるのです。
このような事態を未然に防ぐには、特定の者(後継者)へ株式を相続させる旨の「遺言」の作成が大切です。
ぜひ、弊社で “「遺言信託」の活用” をご検討ください!!
あわせて読みたい!
 |  |
| 事業承継税制の認定取消事由 | 事業承継税制の前に自社株式の評価額を下げる:①役員退職金の利用 |
サービスのご案内
 |  |  |
| 日税経営革新等支援サービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。
株式会社日税経営情報センター